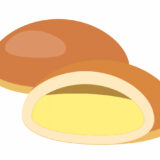赤ちゃんに小豆を与えていいの?小豆は赤飯や和菓子のあんこに使われている食材ですが、赤ちゃんに食べさせても大丈夫なのでしょうか?
今回は、赤ちゃんに小豆を与える時期や、調理方法、注意点などをご紹介します。
おはぎなどおいしい食べ物があると赤ちゃんにもあげたくなりますよね。
おいしいものは一緒に共有したいですし、赤ちゃんの方から「食べたい」といってくる可能性があるのではないでしょうか。
ですが、赤ちゃんにあんこはいつから食べさせて良いのか知っていますか?では、紹介したいと思うので参考にしてくださいね。
前回の記事は 赤ちゃんがカスタード食べるのはいつから大丈夫?食べられる年齢と注意点 でした。
こちらもぜひご覧ください。
赤ちゃんに小豆を与えていいの? 赤ちゃんに小豆を与える時期はいつから?
赤ちゃんに小豆を与える時期は、生後7~8ヶ月頃からが目安です。
小豆は鉄分や食物繊維が豊富に含まれているため、赤ちゃんの成長に必要な栄養素を補うことができます。
しかし、小豆は消化しにくいため、裏ごししたり、皮を取り除いたりして、赤ちゃんが食べやすいように調理しましょう。
赤ちゃんに小豆を与える調理方法
小豆の調理方法は、以下の通りです。
- 小豆をよく洗う。
- 水をたっぷり入れ、火にかける。
- 沸騰したら、弱火で30分ほど煮る。
- 小豆が柔らかくなったら、裏ごしする。
小豆を与える際には、以下の点に注意しましょう。
赤ちゃんに小豆を与える注意点
- 小豆に砂糖や塩を加えないこと。
- 小豆を多量に与えないこと。
- 小豆を与えた後に、赤ちゃんの様子をよく観察すること。
赤ちゃんに小豆を与えることで、鉄分や食物繊維が補給でき、健康的な成長を促すことができます。
ただし、小豆は消化しにくいため、赤ちゃんが食べやすいように調理し、与えすぎに注意しましょう。
あんこの成分は
あんこは砂糖と小豆でできています。小豆自体は食物繊維、ミネラル、たんぱく質がたっぷり入った、体にいい食べ物なので、とてもいい食材です。
なので、あんこも赤ちゃんに食べさせて良いのかといったらそうではありません。
実はあんこは傷みやすい食材なので、少し慎重になる必要があるのです。
甘いので気を付けて
また、あんこはかなり甘いですよね。
だからこそ、すごくおいしいのですが、この砂糖をかなり気をつけなければいけません。
味覚を形成している時期に砂糖を使ったあんこを食べさせるのはあまり良くありません。
小さいときに甘いものを食べてしまうと、甘さへの感覚が狂い、普通の食事を食べなくなってしまう可能性があります。
甘いものは欲しがる
赤ちゃんは栄養のことなど考えて食べ物を欲しがらないので甘いものをすぐに食べたがります。
ですので、早いうちから甘いあんこを教えてしまうと、甘いものしか食べたがらなくなり、すごく危険なのです。あんこを食べさせるのは早くても2歳、3歳くらい幼児になってからにしてくださいね。
あんぱんやどら焼きはいつから?
あんこだけ食べるということは少ないですよね。
あんぱんやどら焼きからあんこを食べるということが多いのではないでしょうか。
離乳食の後期に入った頃からならあんこの部分は避けてパンの皮の部分を少しだけあげることは可能です。
ただ、あんこはこの時期にはまだ早いので食べさせないようにしてくださいね。
あんこが入った、あんぱんやどら焼きはやはり、2~3歳幼児になって以降が良いですね。
将来の味覚や健康のためには、甘いものは早いうちから教えない方が良いです。
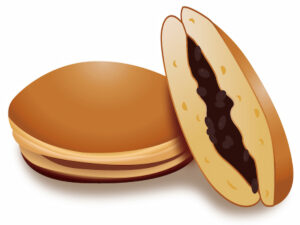
どら焼き
あんこのアレルギーは?
あんこは小豆なので、アレルギーになることは少ないといわれています。
ですので、そこまで慎重に食べさせる必要はないですが、ただ、0とは言えないので少し気にしてあげる必要があります。
もし、アレルギーがある子なら、初めてあげる際には、重症化を避けるために、与える量を少量にしておく方が良いですね。
甘いものが与える影響は?
甘いものが嫌いな子供はいないと思います。
もちろん、大人も大好きな人が多いですよね。
大人は甘いものをよく食べているのに、何故あかちゃんは食べさせない方が良いのかについて紹介します。
- 味覚が乱れて好き嫌いの元になる
- 肥満や生活習慣病になりやすい
- 栄養が偏る
- 低血糖症につながる可能性がある
これらの理由があるので、赤ちゃんには甘いものを食べさせない方がいいといわれています。
また、大人と違って赤ちゃんは我慢することができませんよね。
むしろ栄養のことなど一切自分では考えません。
ですので、好きなものを好きなだけ食べてしまうので、甘いものはできるだけ食べさせない方が良いのです。
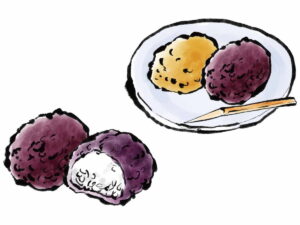
あんこおはぎ
肥満を避けるためにも
赤ちゃんの頃から肥満になるのもかわいそうですよね。
できれば、健康体でいて欲しいでしょう。そのためには、味覚をしっかりさせるように甘いものはあまり食べさせない方が良いです。
もし、どうしてもどら焼きやあんぱんを食べさせるなら、量を決めて少量だけあげるようにしましょう。
理想は3歳からがおすすめ
また、砂糖の甘さは3歳までは必要がないといわれており、果物などの自然な甘さで十分と言われています。
ですので、砂糖を使った甘いものを食べさせるのは3歳幼児以降がいいといわれています。
小豆自体は生後7~8ヶ月頃から食べられる
あんこは砂糖が多いため、2~3歳以降といわれていますが、小豆自体は7~8ヶ月頃から食べてもいいと言われています。
ただ、皮は飲み込みずらく喉にひっかかってしまうので取り除いてください。
皮は消化されにくいので、奥歯が生えてしっかりと噛めるようになってから与えることが大切です。
小豆だけを柔らかく
あかちゃんに小豆を与えるときは、塩や砂糖を使用せずに、お湯でやわらかく煮た「水煮」を使用するようにしてくださいね。
小豆は栄養価が高いものなので、食べられる時期になったら積極的に与えてあげてくださいね。

小豆
本日のポエム
子育ての出発点に立った。
どんな子に育ってほしいか、ふと考える。
どんな子育てをしたいのか。赤ちゃんの将来を見つてしまう。
たぶん親となって最初の仕事なのではないだろうか。
やっぱり健康で健やかに育って欲しい願いを込めて名前を付ける。
まとめ
赤ちゃんに小豆を与える時期は、生後7~8ヶ月頃からが目安です。
小豆は鉄分や食物繊維が豊富に含まれているため、赤ちゃんの成長に必要な栄養素を補うことができます。
しかし、小豆は消化しにくいため、裏ごししたり、皮を取り除いたりして、赤ちゃんが食べやすいように調理しましょう。
このように、赤ちゃんはあんこをいつから食べさせてもOKについて紹介しました。
赤ちゃんの離乳食などは何をいつから与えたら良いのか分かりませんよね。
今は本なども売っているので、それを参考に離乳食を作るもの良いですね。
あんこは甘いものなので、小さい時期からはNGですが、小豆なら離乳食で食べさせることができます。
赤ちゃんの栄養のためにもいろいろ工夫して食べさせてあげることをおすすめします。
次回の記事は 赤ちゃんに果物を与える時期は?アレルギーの心配はある?果物別に解説! です!お楽しみに!
 いろんないつからサイト
いろんないつからサイト